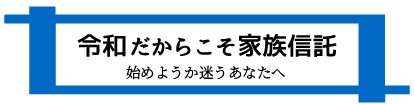家族信託で不動産を売却した時の注意点とは?
家族信託を活用して不動産を売却するケースが増えています。特に認知症などにより財産の凍結リスクが高まる中、信託による柔軟な資産管理は有効な対策となります。
しかし、その実務には細やかな配慮が必要です。とくに売却によって得られた「代金の扱い」を誤ると、思わぬ課税や家族間トラブルにつながることもあります。
本記事では、家族信託の基本構造をおさらいしつつ、不動産売却時の手続き、売却代金の名義・管理・税務、そしてトラブル予防のための具体策について、実務経験に基づいて詳しく解説します。
家族信託とは?基礎からおさらい
家族信託の活用にあたっては、その法的な枠組みと運用の原則を正しく理解しておくことが大切です。特に、不動産という高額資産を信託する場合には、契約内容の明確さがその後の売却や資金管理に直結します。
家族信託の基本構造と登場人物
家族信託は、「委託者(財産の所有者)」「受託者(財産を管理・処分する人)」「受益者(財産から利益を受ける人)」という3者の関係で成立します。
たとえば、高齢の父(委託者・受益者)が、自宅不動産の管理と売却を子(受託者)に託す場合、信託契約によって法的な関係性が構築されます。
ここで重要なのは、名義が受託者に変わったとしても、「財産の本質的な所有者」は受益者である点です。名義と実質を切り分ける信託の仕組みが、のちの資金管理や税務上の根拠にもなります。
不動産を信託財産に含めるメリットとは
不動産を信託に組み入れることには、大きく以下の3つのメリットがあります。
- 認知症発症後も売却が可能になる
成年後見制度では不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要で、非常に煩雑です。信託なら、発症後もスムーズに売却できます。 - 相続トラブルの予防
信託で受益権の帰属先をあらかじめ定めておくことで、「誰がいつどの財産を引き継ぐか」を明確にできます。遺産分割協議が不要な場合もあり、争族の予防策になります。 - 柔軟な承継設計が可能
たとえば「配偶者が亡くなったら子に承継させる」「特定の子にだけ賃貸収益を与える」といった設計ができるのも、信託ならではの特徴です。
家族信託における不動産売却の仕組み
信託された不動産を売却する際には、通常の不動産売買とは異なる注意点が複数存在します。適切な準備と理解が不可欠です。
売却時の手続きと必要書類
売却時にまず必要となるのは、「信託の存在を証明する書類」です。具体的には以下の書類が求められます。
- 信託契約書(原本)
- 登記事項証明書(信託目録付き)
- 受託者の印鑑証明書と本人確認書類
- 売買契約書・媒介契約書(不動産会社経由の場合)
信託が設定されていても、登記上の名義が旧所有者(委託者)のままでは売却できません。信託登記(受託者名義への変更)を完了させておくことが前提です。
また、売買契約書への署名も「受託者」が行うため、不動産会社や司法書士にも信託契約の内容を正しく理解してもらう必要があります。
売却は誰ができる?委託者・受託者の役割
売却に関する意思決定および契約の主体となるのは「受託者」です。たとえ実質的に財産の利益を得るのが委託者(兼受益者)であっても、法的には受託者が売主として契約に臨みます。
しかし、ここで落とし穴となるのが「売却権限の不備」です。信託契約書に明示的な記載がなければ、受託者が単独で売却することはできません。
「必要があれば売却してよい」といった曖昧な表現も、トラブルの原因になり得ます。売却を想定している場合は、「〇〇不動産を〇年以内に市場価格で売却することができる」など、具体的な文言を盛り込んでおくことが望ましいです。
売却代金の扱いと管理方法
売却後の資金は、ただの現金ではありません。引き続き「信託財産」として適切に管理することが求められます。そのための仕組みや注意点を見ていきましょう。
売却代金は誰のもの?信託口口座の必要性
売却代金は受託者が一時的に預かる形になりますが、それはあくまで信託契約に基づく「業務の一環」であり、受託者個人のものではありません。
そのため、資金の入出金には必ず「信託口口座」(受託者個人名義+信託名義)を用いる必要があります。
仮に、受託者が自分の個人口座で代金を受け取った場合、「名義預金」と見なされ、税務署から贈与と判定される可能性があります。これを防ぐには、
- 口座名義を「〇〇太郎 信託口」などと明記する
- 取引記録や支出先を帳簿として残す
- 定期的に信託の状況を受益者に報告する
といった運用の徹底が不可欠です。
税金はどうなる?課税リスクと対策
家族信託による不動産売却は、課税関係が非常に複雑です。主に以下の3つの税金が関わってきます。
- 譲渡所得税(所得税・住民税)
信託設定前の所有者=受益者である場合、売却による譲渡所得はその受益者に帰属します。売却益が出た場合は、一般の不動産売却と同様に課税されます。特例(3,000万円控除など)が適用できる場合もあります。 - 贈与税
売却代金を別の家族に自由に使わせると、「贈与」と見なされることがあります。信託契約に基づかない資金移動は、税務上の否認リスクを伴います。 - 相続税
信託終了後、残余財産が受益権を持たない人に渡ると、相続税ではなく贈与税の対象となる場合があります。
※複数の受益者がいる場合には、按分や配当方法にも注意が必要です。税務上の取り扱いが変わるため、専門家による事前確認が推奨されます。
よくあるトラブルとその回避法
信託は「契約」がすべての基本となる制度です。逆に言えば、契約内容が曖昧であったり、実態と乖離していれば、たとえ形式が整っていてもトラブルは避けられません。
受益者間の争いを避けるには
よくあるのが、「兄が受託者として売却したが、弟には一切説明がなかった」という不信感からのトラブルです。
信託契約における受益者の権利と、受託者の義務(忠実義務・善管注意義務)を明記することが前提ですが、それに加えて「説明責任」や「収支報告義務」など、信託の運用ルールを家族全体で共有しておくことが効果的です。
税務署から否認されるケースとは
たとえば、実質的に親の生活資金に使われていない、契約書と違う名義で金銭が管理されているなど、形式と実態が一致していないと、「信託は名ばかりで実質は贈与」と税務署に判断されてしまいます。
特に相続税対策を意図した信託では、実態が厳しく審査される傾向にあるため、帳簿や報告資料の保管も欠かせません。
専門家に相談すべきタイミングとは
信託の設計段階であれば「司法書士」や「弁護士」が契約内容を整理し、登記の準備を行います。一方、税務面での判断や申告が必要な場合は「税理士」の関与が必須です。
また、信託の運用中や終了時に新たな課題が発生することもあります。そうした際には、信託実務に通じたファイナンシャルプランナーなどと連携し、総合的に判断する体制が理想的です。
よくある質問(FAQ)
家族信託で売却する際のよくある質問とその答えがこちらです。
Q. 家族信託で売却した場合、売却代金の名義は誰になりますか?
A. 売却代金は信託契約に基づき、信託口口座で受託者が管理しますが、受益者の財産として扱われます。名義は受託者ですが、実質は受益者のものです。
Q. 売却代金に贈与税がかかるケースはありますか?
A. 売却代金を受益者以外が自由に使った場合、贈与と見なされ課税される恐れがあります。契約に基づいた使途と受益者の設定が不可欠です。
Q. 売却後に使い道を制限されることはありますか?
A. 信託契約に使途制限がある場合、その範囲内でのみ使用可能です。自由に使いたい場合は、契約内容をあらかじめ調整しておく必要があります。
まとめ
家族信託を通じた不動産売却は、高齢者の財産管理や相続対策として大きな効果が期待できますが、その反面、売却代金の扱いには慎重さが求められます。
形式だけでなく、契約内容と実態の整合性、税務上の根拠、家族内の合意形成――これらをすべて丁寧に整えて初めて、「円満な信託運用」が実現します。